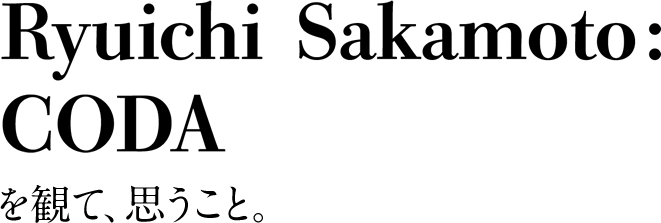[ 対談 ]『Ryuichi Sakamoto: CODA』を観て、思ったこと。長嶋りかこさんと中島佑介さんの場合

グラフィックデザイナーの長嶋りかこさんが、ブックショップ『POST』のオーナーで、TOKYO ART BOOK FAIRのディレクターの中島佑介さんを誘って、映画『Ryuichi Sakamoto: CODA』を観に行きました。その帰り際のふたりの対話。映画の話から、自分たちのクリエイションの話まで。
長嶋
音楽家としてだけでなく、いち人間としての坂本さんの姿勢に対して共感する部分がすごく多いんです。そんなこと言うととても恐縮なのですが……。これまでお仕事をご一緒させて頂いて坂本さんがどのように何を考えて生きてこられたのかを、断片的にでも言葉で聞いたり読んだりする機会が多かっただけに、映画の中で言葉でなく音楽で表現されてフワッと包まれるあの時に、思わず胸が「うっ」っときてしまいましたね。
中島
確かに。映画を観た後に音楽を聴くと、また全然違う感じになるかもしれないなって思いますね。
長嶋
私はもう冒頭からダメ……、勝手に走馬灯のように坂本さんの活動が浮かんで、冒頭で泣いちゃってました(笑)。
中島
あのピアノの音色とかですよね。
長嶋
今回、この映画に中島くんを誘ったのは、まず中島くんって釣り好きじゃない?(笑)。そして今、根室でいろいろとやっていますよね。それで、中島くんの自然との向き合い方に、なにか共通する部分があるんじゃないかなと思って。
中島
はい。あ、根室の風景って、坂本さんの音楽と共通する部分があるんじゃないかなってすごく思いました。色で表すと、深い青のような。坂本さんの90年代以降の環境に対する感覚は、最近のものなんですかね。
長嶋
でも、映画の中の若い頃のインタビューで既に今と同じようなことを言ってましたよね。
中島
はい。言ってました。言ってました。
長嶋
本当にずっとブレてないんだよね。すごいよね。坂本さんの生き様が本当に好き(笑)。もちろん音楽もずっとブレてない。表現の方法だったり、使う楽器はいろいろ変わっていると思うけど、常に同じ音楽があるというか。むしろ、今やっていることは大学時代に戻ったってどこかで言ってたし。
中島
大学時代ってことは……、ピアノってことなんですかね?
長嶋
いや、実験的なことを改めてやっているってことだと思う。
中島
僕が興味深かったのは、曲作りの時の一本目の線の引き方というか、どこからスタートすのるかがすごく感覚的だったところ。作ろうとしているものに合った音を録っているのではなくて、まず音を録ってみて、それを聴いてから出来上がっていくところですね。テクノとかってすごく構築的に作っていくイメージがあったんだけど、坂本さんの場合、そうではなく本当に直感的にやっていて、それが面白いなと思いました。
長嶋
コンセプチュアルな音楽もたくさんあるから、てっきりそこありきでスタートするのかなと思っていたけど、全然違ったよね。以前、坂本さんと「ものを作る時に何で決めているのか」みたいな話をした時、コンセプトと感覚、どちらもあるけど一番最後は感覚、と言ったら、「やっぱり、そうだよね」と同意されていました。ただ、建築家とかだったらそうはいかないから、 坂本さんは「自分は建築家じゃなくてよかった」って言っていましたけど(笑)。
中島
大きくは2つのタイプがあって、頭で考えたものから入る人と、直感から入ってそれを理論化していく人。多分、坂本さんは後者で、りかこさんもそうだと思うんだけど……。
長嶋
コンセプトが最初にあることもあるし、漠然とした感覚的なイメージが最初にあることもあります。
その後はちょっと辻褄を合わせたり、判断する時の材料として理論を取り入れていったり。コンセプトに気をとられて「あれ?なんかすごくつまんなくなっちゃった」って時はまた最初から貘とした感覚を優先してやり直すこともありますね(笑)。

長嶋
映画の中の坂本さんの言葉で「消えない音を作りたい。自分が死ぬまでに恥ずかしくないものを残したい」っていう言葉があったじゃないですか。中島さんもそういうことを思ったりしますか?
中島
そう思うこともあります。ただ、まだまだ自分を俯瞰し切れていないので、今は社会的価値と自分の感覚のどちらかと言うと、自分の感覚が一番納得するところに従っているのかもしれません。それでもだいぶ変わりました。22歳の頃、自分が本屋を始める時は自分の感覚だけでしたからね。
長嶋
それはどういう感覚?
中島
最初、古本屋でスタートして、そこで取り扱っていたものは全部自分で買い付けに行って、自分が良いと思って選んだものだけだったんです。それが、本屋ってもうちょっと公共性のあるべきものなんじゃないかって思って、それで出版社という単位にして、もう少し幅の広いものを扱えるように変えたのが2011年くらいでした。だから、徐々に社会だったりとか、文化だったりとか、 そういったものにもコミットしたいなと思った結果、今の本屋のスタイルになっています。坂本さんはどうだったんですかね?『ラストエンペラー』って何年でしたっけ?自分の母親が、あの映画が好きで良く覚えてるんです。あ、1987年。じゃあ、35、6歳の時なんだ。
長嶋
え!?その歳であの生き方はすごいね。
中島
すごいですね。
長嶋
こんなこと言うレベルじゃないけど、焦るよね(笑)。
中島
焦りますね。20代の頃ってそんなこと思わなかったけど、最近は焦る気持ちはあるかもしれません(笑)。
長嶋
あの年代に、あの作り方で、ものすごいスピード感で制作していて。以前、坂本さんに病気をしてからの坂本さんの仕事のスピード感がすごいなあと思って、「そのスピード感は昔からなんですか?」って聞いたら「病気してから、以前の5分の1のスピードだよ」っておしゃっていて(笑)。なんかもう圧倒的な才能……。
中島
こういう曲を作ろうと思って作っているのではなく、ある音を聴いて、いいなと思ったらそこからスタートするみたいな判断基準だとしたら、仕事の速さにもつながるのかなとも思いました。
長嶋
映画の中でも、この音色が「好き」「好きじゃない」っていうのを、例えば「あのニットちょっと着心地悪いな」なんて肌触りみたいな感じで判断されていたじゃないですか。そういう肌感覚のような生理的なものが耳にあるから、すごく速いのかもしれないよね。
中島
僕、最近、自分の境界線を曖昧にしておくことって、大事だと思っているんです。自分が 釣り好きなのも、根室にすごく興味があるのも、自分の境界線がすごく曖昧になる感覚があるからなんです。
長嶋
釣りの場合は?
中島
自分が溶ける感じ。言い換えると、自分が環境の一部になっちゃうような感じ。根室に行った時や釣りをしている時、あとサウナもそうなんですけど(笑)、すごく近い感覚なんです。その感覚が冴えている時だからこそ気がつくことがある。だから、最近では、そんな感覚を意識的に自分の身体に作っておくのは大事なのかなって思っています。
長嶋
それって中島さんがお店で本を選ぶ時にも関係したりするんですか?
中島
多分、関係していると思います。坂本さんも、音をレコーディングするためにどこかに行くのではなくて、常に移動していて、それがいろいろと次の曲に繋がっていくんだと思うんです。そういう風にいろんなところで得た感覚が、例えば3年後に形になったりするのかもしれません。
長嶋
「こんなリアクションとして出てきたんだ!」みたいなのは、面白いですよね。ある大きな出来事があって、そこに強烈に思うこと、考えることがあったから、その結果として3年後にこういうものが作れたんだなとか。
中島
本屋って本を売る仕事ですけど、自分の場合は今の形になっているのは、やっぱり震災も大きかったと思います。その時にはわからなかったとしても、結果として。

長嶋
世代とかって感じます?私は時代背景はもちろんあると思うけど、環境によって変わるものもあると思っていて。戦後に、ものづくりをしてきた人の感覚って、やっぱり全部無くなった後を新しいもので埋めるようにどんどん作っていこうっていう気持ちになっていったのだろうと思うし、そのパワーってすごい速度とボリュームですよね。今の時代はもういろいろあるから、そういう気持ちになり辛い。でも、そのパワーとボリュームではなく人が根源的に持っているものって、時代は関係ないのかな?とも思う。
中島
自分もそれをすごく思います。「昔の時代は良かった」みたいなことって、常にそうなんじゃないかなって。昔に憧れても仕方なくて、その時代に合った在り方だったりとか、生き方があるわけで。それがずっと継続しているわけだから、あんまり時代のせいにしちゃいけないなって思います。
長嶋
80年代の坂本さんがメイクして喋っているシーンとかは時代のリアリティを感じずにはいられないけど、やっぱり言っていることは今とほとんど変わらない。もちろん時代背景があるからこそ出来たこともあると思うけど、根本的なところは時代のせいじゃないなっていうのがはっきり映っていて、あのシーン大好き。自分がその時代にいたらどうなっているのかな、とはちょっと思いますけど。その熱狂の中にいたら、何をやっているのかなって。
長嶋
私、自分で自分の作ったものに救われることがあるんです。自らが何かを産むときに、自分自身がそれをせずにはいられない切迫性のあるものの場合は、特に実感します。神様がいるかいないかなんて、それは本当に勝手に人間が言っているだけなのに、それがなかったら生きていけない人もいる。映画のなかで、バッハに対して坂本さんが曲に祈りを感じるっていうのは、 癒しのような、救いのような、祈りのような音楽が生まれるべき背景があったということをおっしゃっていましたよね……。多分、世の中の人々だけでなく、バッハ自身もすごく辛いことがたくさんあって、あの曲があったことによって、彼自身も救われることがあったんじゃないかって見ていて思いました。前にアニッシュカプーアへのオマージュとしてのインスタレーションを依頼されてやったんですけど、その時の私が実は精神的にそれをやらざるを得ないというか、「私、これをやらないと死ぬかもしれない」っていうギリギリの感覚だったんです。いつの間にか、全く理性的でも客観的でもなく、もはやただ自分のために作っていました。本来はデザインの仕事って、依頼を受けてから、その対象の思想をどう翻訳してかたちにしていくかっていう、かなり理性的な作業だったりするんです。だけど、あのインスタレーションの仕事の場合、一応、依頼仕事なのでその延長線上ではあるんだけど、カプーアの思想を理解して自分なりの解釈をしてから、自分の背景とともにかたちにしていかなければオマージュにはならないなと思うと、自分の体に起こってきたこと全てを外に出すような感覚で、もう途中から自分の子供のように扱って、本当に自分の心を救うために作ったところがあったんです。
中島
クライアントワークじゃなくて、自分のクリエイションっていうものが率直に反映された作品ってそれまでにもありましたか?
長嶋
実は、大してなくて……。自然と人間の調和をテーマにした作品を作っていたことはあります、というか今も作ってます(笑)。私は、自分が暮らしていた半自給自足の田舎で感じていたことを基にして、デザインがどう自然に対して向き合うことができるかっていうのが結構課題だったりするんです。壊していくことの方が多いんです、デザインの仕事って。 産んでいると同時に壊している作業だから。それへのジレンマみたいなところがあって。いかにして仕事をしながら自然と対峙できるのかなっていう部分の答えが出なくて、それで行き場のない作品を作ったりしていたんです(笑)。自分がやっていることに自分が救われることって、中島さんはあります?
中島
うーん、でも、やっぱりありますね。根源的なところはそれかもしれない。一番やりたいことっていうのが、新しい価値を紹介したり、知ってもらうことで、それで喜んでもらえたりとか、 それが間接的に何か新しいものに繋がったりしているのを見ると、自分がそれで救われる感じはありますね。
長嶋
何のために自分が生きているのかなって思っちゃうから。なんのために私は生まれきて、この身体を使って、この仕事をしたり、いろんな人に出会ったりしているのかなって思うことがあるから、 出てきたものによっては、生きててよかったなって思うんです。そういうものを産める機会を増やしたいですよね。たくさんのことを経て、自分は何のために生きて、デザインをやっているんだっていうのは出していかないとなあってちょうど思っている時です。
中島
それは作品として?それとも言語化するってこと?
長嶋
両方ですね。デザインをするってなると依頼主ありきなので、どういう人たちと一緒に仕事をしていくのかっていうことはすごく大事で。出会う人もそうだけど、デザインをするべきところでやっていきたい。それとは別に、自分が見たいもの、自分がどうしてもかたちにしたいものも作りたい。だから、改めて、坂本さんの音楽を聴いてみようって思いました。
中島
そうですね。普段、音楽を聴く時って、ながら聴きというか、対峙して聴くことがないから、坂本さんが音楽聴く時に目をつぶって聴いていたのがすごく印象的、そうやって音楽だけに向き合う様な聴き方をしたらどうだろうなって思いました。あとは今日、映画館に誘ってもらってすごくよかったなって。普段、映像見るのってそんなに大きくない画面だったり、自分で観ていると単調なところはスキップしちゃったりするじゃないですか。それができないっていう状況で観るのがすごく良かった。それって映画館ならではだし、こうやって観終わった後に話ができるのもあの大画面と良い音響で同じ体験をした後だからだし、映画館で見るって改めていいなって思いました。

長嶋りかこ
グラフィックデザイナー
1980年茨城県生まれ。2003年武蔵野美術大学視覚伝達デザイン科卒業。2014年デザイン会社「village®」設立。グラフィックデザインを基軸に、ブランディング、CI、VI、プロダクトデザイン、パッケージデザイン、エディトリアルデザイン、サイン計画、アートディレクションなどを手がける。
中島佑介
ディレクター
1981年長野県生まれ。株式会社リムアート代表取締役。2002年、古書&インテリアショップ『limArt』をオープン。2010年、『limArt』の姉妹店にあたる『POST』をオープン。 2013年より恵比寿の『limArt』に『POST』を統合。現在はPOSTのディレクターとして、ブックセレクトや展覧会の企画、書籍の出版、その他Dover Street Marketのブックシェルフコーディネートも手がける。2015年よりTHE TOKYO ART BOOK FAIRの共同ディレクターに就任。
一本目の線の引き方。
長嶋
音楽家としてだけでなく、いち人間としての坂本さんの姿勢に対して共感する部分がすごく多いんです。そんなこと言うととても恐縮なのですが……。これまでお仕事をご一緒させて頂いて坂本さんがどのように何を考えて生きてこられたのかを、断片的にでも言葉で聞いたり読んだりする機会が多かっただけに、映画の中で言葉でなく音楽で表現されてフワッと包まれるあの時に、思わず胸が「うっ」っときてしまいましたね。
中島
確かに。映画を観た後に音楽を聴くと、また全然違う感じになるかもしれないなって思いますね。
長嶋
私はもう冒頭からダメ……、勝手に走馬灯のように坂本さんの活動が浮かんで、冒頭で泣いちゃってました(笑)。
中島
あのピアノの音色とかですよね。
長嶋
今回、この映画に中島くんを誘ったのは、まず中島くんって釣り好きじゃない?(笑)。そして今、根室でいろいろとやっていますよね。それで、中島くんの自然との向き合い方に、なにか共通する部分があるんじゃないかなと思って。
中島
はい。あ、根室の風景って、坂本さんの音楽と共通する部分があるんじゃないかなってすごく思いました。色で表すと、深い青のような。坂本さんの90年代以降の環境に対する感覚は、最近のものなんですかね。
長嶋
でも、映画の中の若い頃のインタビューで既に今と同じようなことを言ってましたよね。
中島
はい。言ってました。言ってました。
長嶋
本当にずっとブレてないんだよね。すごいよね。坂本さんの生き様が本当に好き(笑)。もちろん音楽もずっとブレてない。表現の方法だったり、使う楽器はいろいろ変わっていると思うけど、常に同じ音楽があるというか。むしろ、今やっていることは大学時代に戻ったってどこかで言ってたし。
中島
大学時代ってことは……、ピアノってことなんですかね?
長嶋
いや、実験的なことを改めてやっているってことだと思う。
中島
僕が興味深かったのは、曲作りの時の一本目の線の引き方というか、どこからスタートすのるかがすごく感覚的だったところ。作ろうとしているものに合った音を録っているのではなくて、まず音を録ってみて、それを聴いてから出来上がっていくところですね。テクノとかってすごく構築的に作っていくイメージがあったんだけど、坂本さんの場合、そうではなく本当に直感的にやっていて、それが面白いなと思いました。
長嶋
コンセプチュアルな音楽もたくさんあるから、てっきりそこありきでスタートするのかなと思っていたけど、全然違ったよね。以前、坂本さんと「ものを作る時に何で決めているのか」みたいな話をした時、コンセプトと感覚、どちらもあるけど一番最後は感覚、と言ったら、「やっぱり、そうだよね」と同意されていました。ただ、建築家とかだったらそうはいかないから、 坂本さんは「自分は建築家じゃなくてよかった」って言っていましたけど(笑)。
中島
大きくは2つのタイプがあって、頭で考えたものから入る人と、直感から入ってそれを理論化していく人。多分、坂本さんは後者で、りかこさんもそうだと思うんだけど……。
長嶋
コンセプトが最初にあることもあるし、漠然とした感覚的なイメージが最初にあることもあります。
その後はちょっと辻褄を合わせたり、判断する時の材料として理論を取り入れていったり。コンセプトに気をとられて「あれ?なんかすごくつまんなくなっちゃった」って時はまた最初から貘とした感覚を優先してやり直すこともありますね(笑)。
自分の境界線を曖昧にする。

長嶋
映画の中の坂本さんの言葉で「消えない音を作りたい。自分が死ぬまでに恥ずかしくないものを残したい」っていう言葉があったじゃないですか。中島さんもそういうことを思ったりしますか?
中島
そう思うこともあります。ただ、まだまだ自分を俯瞰し切れていないので、今は社会的価値と自分の感覚のどちらかと言うと、自分の感覚が一番納得するところに従っているのかもしれません。それでもだいぶ変わりました。22歳の頃、自分が本屋を始める時は自分の感覚だけでしたからね。
長嶋
それはどういう感覚?
中島
最初、古本屋でスタートして、そこで取り扱っていたものは全部自分で買い付けに行って、自分が良いと思って選んだものだけだったんです。それが、本屋ってもうちょっと公共性のあるべきものなんじゃないかって思って、それで出版社という単位にして、もう少し幅の広いものを扱えるように変えたのが2011年くらいでした。だから、徐々に社会だったりとか、文化だったりとか、 そういったものにもコミットしたいなと思った結果、今の本屋のスタイルになっています。坂本さんはどうだったんですかね?『ラストエンペラー』って何年でしたっけ?自分の母親が、あの映画が好きで良く覚えてるんです。あ、1987年。じゃあ、35、6歳の時なんだ。
長嶋
え!?その歳であの生き方はすごいね。
中島
すごいですね。
長嶋
こんなこと言うレベルじゃないけど、焦るよね(笑)。
中島
焦りますね。20代の頃ってそんなこと思わなかったけど、最近は焦る気持ちはあるかもしれません(笑)。
長嶋
あの年代に、あの作り方で、ものすごいスピード感で制作していて。以前、坂本さんに病気をしてからの坂本さんの仕事のスピード感がすごいなあと思って、「そのスピード感は昔からなんですか?」って聞いたら「病気してから、以前の5分の1のスピードだよ」っておしゃっていて(笑)。なんかもう圧倒的な才能……。
中島
こういう曲を作ろうと思って作っているのではなく、ある音を聴いて、いいなと思ったらそこからスタートするみたいな判断基準だとしたら、仕事の速さにもつながるのかなとも思いました。
長嶋
映画の中でも、この音色が「好き」「好きじゃない」っていうのを、例えば「あのニットちょっと着心地悪いな」なんて肌触りみたいな感じで判断されていたじゃないですか。そういう肌感覚のような生理的なものが耳にあるから、すごく速いのかもしれないよね。
中島
僕、最近、自分の境界線を曖昧にしておくことって、大事だと思っているんです。自分が 釣り好きなのも、根室にすごく興味があるのも、自分の境界線がすごく曖昧になる感覚があるからなんです。
長嶋
釣りの場合は?
中島
自分が溶ける感じ。言い換えると、自分が環境の一部になっちゃうような感じ。根室に行った時や釣りをしている時、あとサウナもそうなんですけど(笑)、すごく近い感覚なんです。その感覚が冴えている時だからこそ気がつくことがある。だから、最近では、そんな感覚を意識的に自分の身体に作っておくのは大事なのかなって思っています。
長嶋
それって中島さんがお店で本を選ぶ時にも関係したりするんですか?
中島
多分、関係していると思います。坂本さんも、音をレコーディングするためにどこかに行くのではなくて、常に移動していて、それがいろいろと次の曲に繋がっていくんだと思うんです。そういう風にいろんなところで得た感覚が、例えば3年後に形になったりするのかもしれません。
長嶋
「こんなリアクションとして出てきたんだ!」みたいなのは、面白いですよね。ある大きな出来事があって、そこに強烈に思うこと、考えることがあったから、その結果として3年後にこういうものが作れたんだなとか。
中島
本屋って本を売る仕事ですけど、自分の場合は今の形になっているのは、やっぱり震災も大きかったと思います。その時にはわからなかったとしても、結果として。

時代によって変わること、変わらないこと。
長嶋
世代とかって感じます?私は時代背景はもちろんあると思うけど、環境によって変わるものもあると思っていて。戦後に、ものづくりをしてきた人の感覚って、やっぱり全部無くなった後を新しいもので埋めるようにどんどん作っていこうっていう気持ちになっていったのだろうと思うし、そのパワーってすごい速度とボリュームですよね。今の時代はもういろいろあるから、そういう気持ちになり辛い。でも、そのパワーとボリュームではなく人が根源的に持っているものって、時代は関係ないのかな?とも思う。
中島
自分もそれをすごく思います。「昔の時代は良かった」みたいなことって、常にそうなんじゃないかなって。昔に憧れても仕方なくて、その時代に合った在り方だったりとか、生き方があるわけで。それがずっと継続しているわけだから、あんまり時代のせいにしちゃいけないなって思います。
長嶋
80年代の坂本さんがメイクして喋っているシーンとかは時代のリアリティを感じずにはいられないけど、やっぱり言っていることは今とほとんど変わらない。もちろん時代背景があるからこそ出来たこともあると思うけど、根本的なところは時代のせいじゃないなっていうのがはっきり映っていて、あのシーン大好き。自分がその時代にいたらどうなっているのかな、とはちょっと思いますけど。その熱狂の中にいたら、何をやっているのかなって。
自分の作ったものに救われる。
長嶋
私、自分で自分の作ったものに救われることがあるんです。自らが何かを産むときに、自分自身がそれをせずにはいられない切迫性のあるものの場合は、特に実感します。神様がいるかいないかなんて、それは本当に勝手に人間が言っているだけなのに、それがなかったら生きていけない人もいる。映画のなかで、バッハに対して坂本さんが曲に祈りを感じるっていうのは、 癒しのような、救いのような、祈りのような音楽が生まれるべき背景があったということをおっしゃっていましたよね……。多分、世の中の人々だけでなく、バッハ自身もすごく辛いことがたくさんあって、あの曲があったことによって、彼自身も救われることがあったんじゃないかって見ていて思いました。前にアニッシュカプーアへのオマージュとしてのインスタレーションを依頼されてやったんですけど、その時の私が実は精神的にそれをやらざるを得ないというか、「私、これをやらないと死ぬかもしれない」っていうギリギリの感覚だったんです。いつの間にか、全く理性的でも客観的でもなく、もはやただ自分のために作っていました。本来はデザインの仕事って、依頼を受けてから、その対象の思想をどう翻訳してかたちにしていくかっていう、かなり理性的な作業だったりするんです。だけど、あのインスタレーションの仕事の場合、一応、依頼仕事なのでその延長線上ではあるんだけど、カプーアの思想を理解して自分なりの解釈をしてから、自分の背景とともにかたちにしていかなければオマージュにはならないなと思うと、自分の体に起こってきたこと全てを外に出すような感覚で、もう途中から自分の子供のように扱って、本当に自分の心を救うために作ったところがあったんです。
中島
クライアントワークじゃなくて、自分のクリエイションっていうものが率直に反映された作品ってそれまでにもありましたか?
長嶋
実は、大してなくて……。自然と人間の調和をテーマにした作品を作っていたことはあります、というか今も作ってます(笑)。私は、自分が暮らしていた半自給自足の田舎で感じていたことを基にして、デザインがどう自然に対して向き合うことができるかっていうのが結構課題だったりするんです。壊していくことの方が多いんです、デザインの仕事って。 産んでいると同時に壊している作業だから。それへのジレンマみたいなところがあって。いかにして仕事をしながら自然と対峙できるのかなっていう部分の答えが出なくて、それで行き場のない作品を作ったりしていたんです(笑)。自分がやっていることに自分が救われることって、中島さんはあります?
中島
うーん、でも、やっぱりありますね。根源的なところはそれかもしれない。一番やりたいことっていうのが、新しい価値を紹介したり、知ってもらうことで、それで喜んでもらえたりとか、 それが間接的に何か新しいものに繋がったりしているのを見ると、自分がそれで救われる感じはありますね。
長嶋
何のために自分が生きているのかなって思っちゃうから。なんのために私は生まれきて、この身体を使って、この仕事をしたり、いろんな人に出会ったりしているのかなって思うことがあるから、 出てきたものによっては、生きててよかったなって思うんです。そういうものを産める機会を増やしたいですよね。たくさんのことを経て、自分は何のために生きて、デザインをやっているんだっていうのは出していかないとなあってちょうど思っている時です。
中島
それは作品として?それとも言語化するってこと?
長嶋
両方ですね。デザインをするってなると依頼主ありきなので、どういう人たちと一緒に仕事をしていくのかっていうことはすごく大事で。出会う人もそうだけど、デザインをするべきところでやっていきたい。それとは別に、自分が見たいもの、自分がどうしてもかたちにしたいものも作りたい。だから、改めて、坂本さんの音楽を聴いてみようって思いました。
中島
そうですね。普段、音楽を聴く時って、ながら聴きというか、対峙して聴くことがないから、坂本さんが音楽聴く時に目をつぶって聴いていたのがすごく印象的、そうやって音楽だけに向き合う様な聴き方をしたらどうだろうなって思いました。あとは今日、映画館に誘ってもらってすごくよかったなって。普段、映像見るのってそんなに大きくない画面だったり、自分で観ていると単調なところはスキップしちゃったりするじゃないですか。それができないっていう状況で観るのがすごく良かった。それって映画館ならではだし、こうやって観終わった後に話ができるのもあの大画面と良い音響で同じ体験をした後だからだし、映画館で見るって改めていいなって思いました。

長嶋りかこ
グラフィックデザイナー
1980年茨城県生まれ。2003年武蔵野美術大学視覚伝達デザイン科卒業。2014年デザイン会社「village®」設立。グラフィックデザインを基軸に、ブランディング、CI、VI、プロダクトデザイン、パッケージデザイン、エディトリアルデザイン、サイン計画、アートディレクションなどを手がける。
中島佑介
ディレクター
1981年長野県生まれ。株式会社リムアート代表取締役。2002年、古書&インテリアショップ『limArt』をオープン。2010年、『limArt』の姉妹店にあたる『POST』をオープン。 2013年より恵比寿の『limArt』に『POST』を統合。現在はPOSTのディレクターとして、ブックセレクトや展覧会の企画、書籍の出版、その他Dover Street Marketのブックシェルフコーディネートも手がける。2015年よりTHE TOKYO ART BOOK FAIRの共同ディレクターに就任。